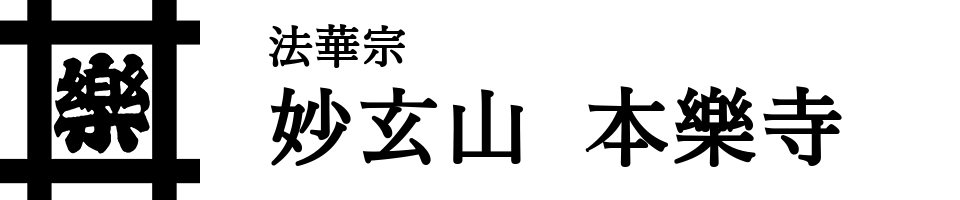仏さまのお供え物について
お仏壇・お墓・お寺の本堂、毎朝晩・故人のご命日・お葬式や年忌法要など場所や場合を問わず、仏さまをお参りする際に最低限必要なものは変わりません。
- 香(線香・焼香に使う抹香など)
- 華(生花・仏壇に備え付けの金蓮華など)
- 燈燭(ローソク)
- 浄水(お茶、水、湯など)
- 飲食(お膳、果物、菓子など)
以上がお供え物の基本となります。
仏さまをお参りする際に仏具を調え、お飾りすることを「荘厳」といいます。
「荘厳」は仏さま参りの最も基本となる重要な修行です。
上記の1~3の香・華・燈燭は「三具足」または「五具足」と呼ばれ、「荘厳」を行う際の基本となります。

三具足

五具足
「三具足」は中央に香炉、向かって左に花瓶、右に燭台を配置します。
「五具足」は「三具足」の華・燈燭がそれぞれ一対ずつになり、中央から香炉、燭台、花瓶の順に配置します。
4・5の浄水・飲食は常に準備が必要なことですから、「必ずこうしなければいけない」という意識で臨むと、お供えすること自体が負担となってしまうことがありますので、できる範囲で無理なく毎日行えるように務めることが肝要です。
 「三具足・五具足」と飲食の「霊供膳」は配置をよくまちがえて荘厳されている方が多いので、特に気を付けていただきたいと思います。
「三具足・五具足」と飲食の「霊供膳」は配置をよくまちがえて荘厳されている方が多いので、特に気を付けていただきたいと思います。
- ※「霊供膳」で特に多いのは「汁椀」と「壺」のまちがえです。
- ※おかずの器(高杯・平椀・壺)の配置は宗派や地域性によって異なる場合があります。
- ※お箸は仏さま側に向けます。
- ※ときどき法事の際にお斎の料理を「霊供膳」の代わりにお供えされる方がおりますが、厳密にはこれはまちがえです。

マッチ消し

お鈴
また、仏壇に置いてある「お鈴」や香炉(線香たて)にマッチの燃えガラを入れているお宅が時々ありますが、いずれも本来の使い方がありますので、やめましょう。
専用のマッチ消し(燃えガラ入れ)か、灰皿などをお使いください。